『真夜中ハートチューン』音響が描く“心のチューニング”──星街すいせいが撃ち鳴らす、夜の共鳴
この作品において「音」は、物語そのものだ。
主人公が“声”を探し、ヒロインたちが“声”で夢を描く。
だからこそ、音楽・音響・主題歌のすべてが作品構造の一部として響き合う。
ここでは、当事者として得られた具体的な音響情報を整理し、その意味を深く掘り下げていく。
確定している「音」関連情報
- 音楽:高橋邦幸(MONACA)
- 音響監督:森田祐一
- 音響制作:月虹/INSPIONエッジ
- OPテーマ:星街すいせい「月に向かって撃て」(作詞:ナナホシ管弦楽団/作曲:岩見 陸/編曲:ナナホシ管弦楽団)
- EDテーマ:Soala「声の軌跡」(作詞:Soala/作曲:Soala、玉木千尋/編曲:玉木千尋)
- 音響制作会社INSPIONエッジ:レコーディング・編集・MAまで一貫体制を持つ音響スタジオ
- 音響監督・森田祐一:『幻日のヨハネ』『ウマ娘』などで知られる精緻な“間”の演出家
- 放送部×深夜ラジオ設定:「聴覚」を主軸にした青春群像。環境音・無音の扱いが物語演出の中心
(参照元:公式サイト/KAI-YOU.net/週刊少年マガジン公式/レーベルニュース各社)
音が果たす“物語装置”としての役割
1. OPは“行為を起動するビート”
星街すいせい「月に向かって撃て」は、作品全体のトーンを決定づける“発信のスイッチ”だ。
公式コメントでは「挑戦する人の背中を押す」と語られ、受け身の主人公を能動へ導く象徴となる。
タイトルの「撃て」という動詞は、夜の静けさを破る衝動そのもの。第2弾PVで流れるサビ部分が、その“行為の起動音”として機能している。
2. EDは“記憶を定着させる残響”
Soala「声の軌跡」は、発した声が届き、記憶に変わるまでの時間を描く。
レーベル発表では「有栖が“声”だけを頼りにアポロを探す映像」と説明されており、
物語の“未決着の感情”を毎話EDの余韻に沈める仕掛けがある。
3. 放送部×ラジオ=可聴世界の再構築
この作品は、視覚ではなく“聴覚”が主役。
音響監督森田祐一の得意とする「台詞間の間」「空間残響の差異」が生きる設計だ。
INSPIONエッジによる音響制作ラインは、マイクノイズ・フェーダー音・機材クリックなど、放送部のリアルな“音の手触り”を再現する体制を持つ。
4. MONACA高橋邦幸の音色設計
高橋邦幸は過去インタビューで「物語に寄り添う音色選択」を重視すると語っている。
彼が本作で描くのは、現実音と内面旋律の融合。
教室の空気振動やマイクのノイズを、透明なシンセや弦の倍音に溶かすことで、
“心がチューニングされる瞬間”を音そのもので体現している。
5. ダイアローグの録りと“夜の静けさ”
『真夜中ハートチューン』では、囁き・息継ぎ・無音の間がそのままドラマになる。
音響監督と声優が距離を計算し、INSPIONエッジのノイズコントロールが
夜の空気を“耳で感じる”レベルにまで研ぎ澄ます。
つまり、音量の小ささ=感情の深さという表現を、制作体制ごとで成立させているのだ。
音響演出を観る・聴く際のチェックポイント
- OP前のSE:無音→クリック→OP頭など、“行為へ切り替わる”設計があるか
- 部室の環境ノイズ:蛍光灯やPCファンなど、日常の音場の描き分け
- ラジオ音声の質感:圧縮音と生声の距離感をEQでどう差別化しているか
- ED入りの落とし:セリフ→環境音→EDイントロのつなぎ方
結語──“音”が心をチューニングする
OPの「撃て」は行為の宣言、EDの「軌跡」は記憶の証明。
そのあいだにある“沈黙”こそ、彼らの心がチューニングされる音だ。
『真夜中ハートチューン』の音響設計は、視聴者自身の胸を鳴らすための構造。
──一話の沈黙が、シリーズ全体の叫びになる。
情報ソース
・『真夜中ハートチューン』公式サイト
・KAI-YOU.net:星街すいせいコメント記事
・週刊少年マガジン公式
・各レーベルニュース/INSPIONエッジ企業情報/MONACA高橋邦幸インタビュー参照(2025年10月時点)



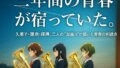
コメント